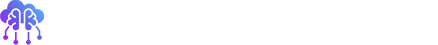はじめに:その画像、本当に使って大丈夫?AIには「全部バレてる」かもしれない話
「みんなやってるから大丈夫」「バレなければ問題ない」。Webでコンテンツを作っていると、そんな風潮を感じることがありますよね。でも、AIの画像認識技術がとんでもなく進化している今、その常識はもう通用しないかもしれません。AIは、コンテンツに潜む権利侵害のリスクを、すでに見抜き始めています。AIには全部バレちゃう、ちょっと怖い世の中になってきたんです。
最近、画像認識AIの精度に衝撃を受けた僕は、今後の肖像権・著作権の問題と、AI検索の評価がどう変わっていくのかが気になって仕方なくなりました。そこで、AI(今回はGoogleのGemini)自身に、このデリケートな問題を直接ぶつけて議論してみることに。その結果を皆さんと共有します。
第一の問い:Web上の「著作権侵害」、AIってぶっちゃけ見抜けるの?
まず、僕がAIに投げかけたのは、素朴だけど核心的なこの質問です。
【僕からの質問】
YouTubeとか見てるとさ、トランプさんとか大谷翔平さんとか、アニメのキャラとか、明らかに許可取ってなさそうな画像やイラストが溢れまくってるよね?有名なチャンネルでさえ、平気で使ってるし。
今のAIって、画像の中身を高精度で読み取れるわけだから、こういう著作権とか肖像権の侵害って、もう技術的には見抜けるんじゃないの?で、将来的にAIがそれを自動で取り締まって、検索の評価を下げたりする未来って来ると思う?
この問いに対して、AIは現状分析から入り、非常に詳細な回答を返してきました。
【AIからの回答】
まず現状として、ご指摘の通りプラットフォーム上には権利侵害の可能性があるコンテンツが溢れています。これは、①権利者による戦略的放置(宣伝効果への期待)、②人力では追いきれない膨大なコンテンツ量、③フェアユースの主張、といった要因が絡み合い、ある種の「グレーゾーン」が黙認されている状態です。しかし、技術的には、マルチモーダルAIは画像や動画内の人物、キャラクターを高精度で識別できます。「この動画には、〇〇社の著作物であるキャラクター画像が、〇秒から〇秒まで無断で使用されている可能性が高い」と自動でフラグを立てることは、すでに可能です。
その上で、ご質問の「AIによる取り締まりと検索評価への影響」は、「ほぼ間違いなく起こる」と予測します。主な理由は3つです。
1. 訴訟リスクの増大: AIが進化すれば、プラットフォーム側は「見つけられなかった」という言い訳が通用しなくなります。
2. AI自身の倫理観: Googleのような企業は、自社のAIが「著作権侵害を助長している」と見なされることを避ける必要があります。
3. E-E-A-T評価の新たな指標: そして最も重要なのが、Googleが提唱するE-E-A-Tの「信頼性(Trustworthiness)」です。「権利関係を尊重しているか」は、サイトの信頼性を測る客観的な指標になります。AIは著作権侵害コンテンツを簡単に見抜けるため、それらをAI検索の参照元から除外したり、評価を下げたりすることは非常に合理的です。
第二の問い:プラットフォームの利益と「第三者機関」の動向
AIの回答は論理的でしたが、僕にはまだ疑問がありました。プラットフォーム側の本音や、外部からの圧力についてはどうなのか。
【僕からの質問】
なるほどね。でも僕は、Google側も動画が回ったほうが利益に繋がるから、あえてグレーゾーンで放置すると思ってたんだ。でも確かに、AIの進化を考えると、「量が多すぎてチェックできない」っていう言い訳は通用しなくなるか。音楽の著作権には厳しいのに、画像やイラスト、肖像権は良いのか?って話だもんね。
あとさ、画像追跡サービスの「COPYTRACK」みたいな専門の第三者機関が、動画コンテンツの権利侵害監視に本格的に乗り出してくる、って可能性についてはどう思う?
この問いで、議論はさらに現実味を帯びてきました。
【AIからの回答】
「COPYTRACK」のような第三者機関が動画分野へ本格参入する可能性は、「極めて高い」と言えます。動画内の画像無断使用の監視は、AI技術の進化により巨大なビジネスチャンス(ブルーオーシャン)となっています。この「外部からの圧力(第三者機関の監視強化)」と、先ほど述べた「プラットフォーム内部の自主規制」が同時に働くことで、権利侵害コンテンツの淘汰は加速するでしょう。
第三の問い:「AI生成イラスト」の肖像権はどうなる?
ここで、さらに現代的な疑問が浮かびました。写真そのものではなく、AIが生成した「そっくりなイラスト」の場合はどうなるのか。
【僕からの質問】
じゃあ、もう一つ。AI画像生成で、トランプさんや大谷選手にそっくりなイラストを作った場合も、肖像権の侵害になるのかな?デフォルメしたり、ちょっと絵柄を変えたりしてもダメ?
この問いには、法律と倫理の両面から、慎重かつ重要な回答が返ってきました。
【AIからの回答】
非常に重要な論点です。結論から言うと、「本人が特定可能であれば、たとえAIが生成したイラストであっても、肖像権(パブリシティ権)の侵害にあたる可能性が非常に高い」です。デフォルメの度合いに関わらず、「誰が見ても〇〇さんだとわかる」状態であれば、本人の許可なく商業利用することはできません。特に、著名人の場合は顧客吸引力を持つ「パブリシティ権」が保護されており、AI生成イラストであってもその権利を侵害し得ます。AIは元画像との類似度や特徴点を比較し、特定の人物との関連性を判断できるため、これもまた将来的に検出・評価対象となるでしょう。
第四の問い:「企業ロゴ」の不正利用も評価を下げる?
最後に、個人だけでなく、企業の権利についても聞いてみました。
【僕からの質問】
なるほど、そっくりイラストも危ないんだね。じゃあ最後に、企業の「ロゴ」について。公式ガイドラインを無視して、勝手に色を変えたり、古いロゴを使い続けたりしてるサイトって結構あるよね。こういうロゴの不正利用も、AIはサイトの信頼性を下げる判断材料にすると思う?
AIは、これもまた「信頼性」に直結する問題だと断言しました。
【AIからの回答】
はい、その通りです。企業ロゴの正しい使用は、その企業への敬意と、情報の正確性を示す重要なサインです。ガイドラインを無視したロゴの使用は、「細部への配慮が欠けた、信頼性の低いサイト運営者である」とAIが判断する格好の材料になります。これもまた、サイト全体のE-E-A-T、特に「信頼性」を損なう要因として評価に組み込まれる可能性は非常に高いです。
まとめ:これからのコンテンツ制作で、絶対に守るべきこと
AIとの議論を通じて、今後のWebコンテンツ制作における重要な指針が見えてきました。
- 無断転載は論外:インターネットから拾ってきた画像や、許諾を得ていない著名人の写真、キャラクター画像は使用しない。
- AI生成イラストも要注意:特定の人物がモデルだと分かるAI生成イラストの商業利用は、肖像権侵害のリスクを伴う。
- ロゴはガイドライン遵守:他社の企業ロゴを使用する際は、必ず公式の利用ガイドラインを確認し、ルールを厳守する。
- 安全な素材の利用:使用する画像やイラストは、自身で撮影・制作したもの、または正規のライセンス契約を結んだストックフォトサービスのものに限定することが最も安全です。
正しい取り組みをする人が、正しく評価されて報われる世の中になって欲しいと思うのは昔から変わりません。ただ、AIの進化による監視社会の加速、徹底的な合理化には息苦しさを感じてしまうのが、僕たち人間という生き物なのかもしれません。
しかし、いずれにせよ、将来的にAIからの信頼を落とさないためにも、今からこうした細かい部分にも気を配っていくことが、サイト運営者にとって非常に大切になるのは間違いないでしょう。
当サイトを運営する株式会社ドリームテラーでは、現状を見るだけでなく、未来を見据えて、こうしたAI時代の新たなリスクに対応し、クリーンで信頼性の高いコンテンツ作りをサポートするコンサルティングも行っています。足元のリスクに不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。