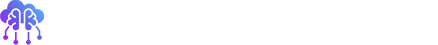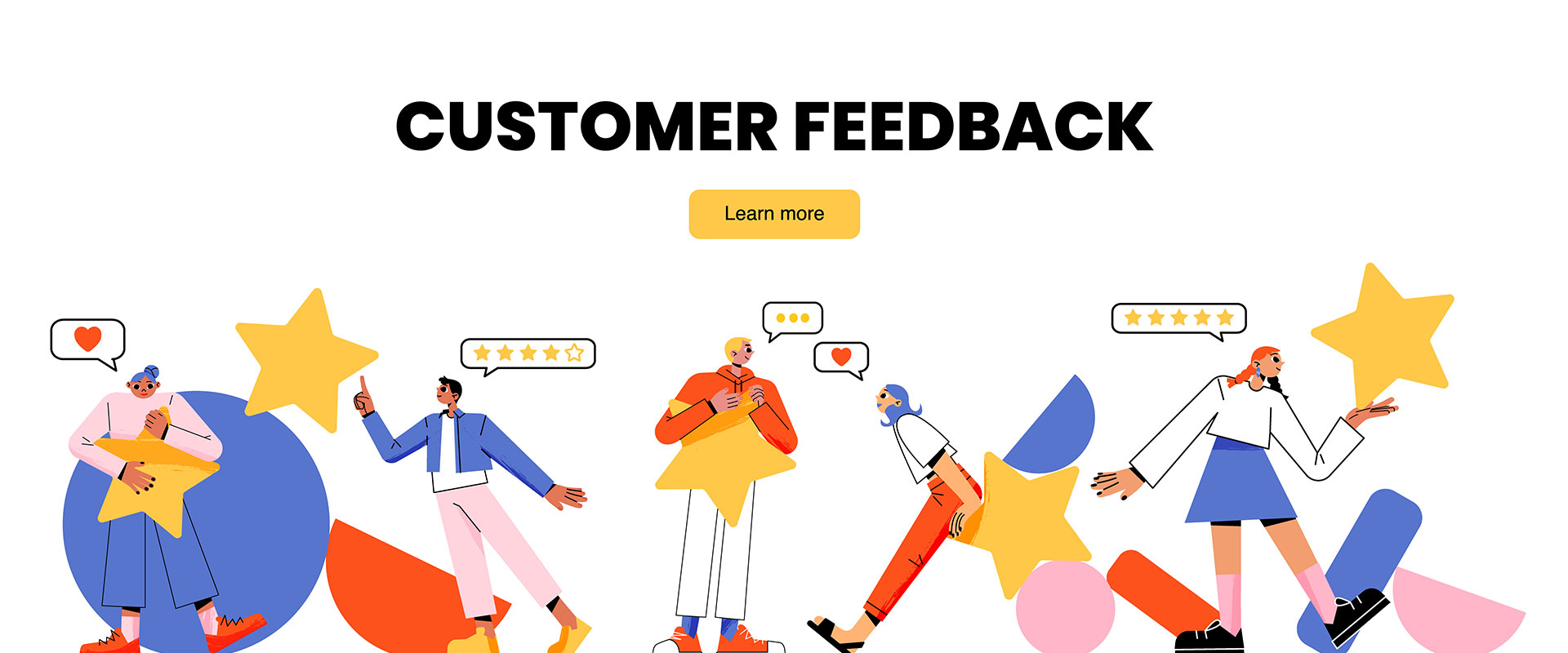はじめに:「良いコンテンツ」の定義が、今、変わろうとしている
長年、私たちは「良いコンテンツとは何か?」という問いに、検索エンジンのアルゴリズムと向き合いながら答えを探してきました。キーワードの配置、網羅性、被リンクの数…。しかし、AIがWebの新しい主役になろうとしている今、その答えの次元が根本から変わろうとしています。
これからの時代、既存の評価軸に加えて、「リアルな顧客満足度」という新しい物差しが、検索結果をもう一段階、高い精度へとチューニングしていくことになるでしょう。
この記事では、なぜ私が「SEOの次の指標は“顧客満足度”になる」と考えるのか、その理由を、AIの驚くべき能力と、Googleが目指す未来から、少しだけ未来を先取りするような気持ちで、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
【根拠1】「検索エンジンは騙せても、AIは騙せない」時代の到来
私がこう考える一番の理由は、近年のAIの進化を見ていて、「もはや、AIはごまかせないな」と、肌で感じているからです。これまでの検索エンジンは、ある意味でとても素直でした。テキストに書かれている情報を、基本的にはそのまま信じて評価しようと努めてくれていたのです。
でも、現代のマルチモーダルAIは、全く違うレベルで情報を「確かめ」にきます。
-
「セミナーに登壇しました」という一文の裏付け:
AIは、その文章だけでなく、ページにある登壇風景の「画像」が本物か、なければ他のニュースサイトやSNSで「あのセミナー、良かったよ」と言及されているかまで、瞬時に確認しにいきます。 -
「〇〇の資格を保有」という記述の信憑性:
AIは、プロフィールに書かれた資格が、公式サイトの正式名称と合っているか、なんなら授与機関のデータベースにその人がいるかまで、確かめる力を持っています。 -
「顧客満足度No.1」という主張の客観性:
AIは、サイト内のアピールだけでなく、Googleマップの口コミ、レビューサイトの星の数、SNSでのリアルな評判といった、Web上に散らばる無数の「お客さんの生の声」を全部まとめて、その主張が本当かどうかを判断します。
このように、AIはテキスト、画像、動画、そしてWeb全体の評判を統合して「事実確認」を行います。もう、サイトの中だけでどれだけ立派なことを書いても、実際の行動や客観的な事実が伴っていなければ、AIにはすぐに見抜かれてしまうのです。
【根拠2】「まとめサイト問題」に、Google自身が向き合わざるを得ない
私がこう考えるもう一つの大きな理由は、今のAI検索が抱える「まとめサイト問題」と、それに対するGoogleの会社としての姿勢にあります。
Webマーケターとして、ちょっと“残念に思う”こと
他の記事でも触れましたが、今のAIは、情報が網羅的にまとまっているという理由だけで、大手メディアや比較サイトの記事を参考にしがちです。長年この業界にいる者として、これは少し残念な状況だなと感じています。
なぜなら、そうしたまとめ記事で紹介されているお店やサービスが、必ずしも「利用者を本当に満足させている優良なもの」とは限らないからです。ただ情報が多いというだけで、中身の薄いコンテンツが評価されてしまうのは、Web全体の質の低下にも繋がりかねません。
Googleの哲学:「ユーザーの体験」こそが全て
でも、この状況を誰よりも「マズイな」と思っているのは、おそらくGoogle自身でしょう。彼らは創業以来ずっと、「ユーザーの検索体験を最高のものにしたい」と言い続けてきました。もしAIの回答が「網羅的だけど、なんかイマイチ」な情報ばかりになったら、ユーザーはがっかりしてGoogleから離れていってしまいます。
だからこそ、GoogleはAIのアルゴリズムをさらに進化させ、単なる情報の網羅性だけでなく、その先にある「リアルな顧客満足度」を、ランキングを最終調整するための重要なシグナルとして、これまで以上に重視せざるを得ないのです。それは、ユーザーのためであり、ひいてはGoogle自身の未来のためでもある、ごく自然な進化だと思います。
“本当の価値”が問われる時代に、私たちがすべきこと
では、この新しい時代に、サイトを運営する私たちは何をすべきなのでしょうか?答えは、驚くほどシンプルで、昔から言われていることかもしれません。
それは、AIを騙そうとするのではなく、ただひたすらに、目の前の一人ひとりのお客さんを満足させるための努力を続けることです。良い製品を作り、誠実なサービスを提供し、お客さんの声に耳を傾け、寄せられた良い評判も、厳しい指摘も、全てを真摯に受け止める。
そうした地道な事業活動そのものが、Web上にリアルな「顧客満足度の証拠」として自然と蓄積されていき、それがAIによって評価されることで、あなたのサイトは「情報が詳しいだけでなく、ユーザーを本当に満足させられるサイトだ」という、一段階上の信頼性を獲得できるのです。
人間同士の信頼構築と、全く同じことです
これって、人間同士の信頼関係の作り方と全く同じですよね。嘘をつかず正直で、もし間違えたら、素直に認めて謝り、同じミスをしないように改善する。完璧でなくても、そうやって真摯に向き合う姿勢があれば、「この人は信頼できるな」と思えるはずです。
逆に、良いことばかり言う人、自分のすごいところばかりアピールしてくる人がいたら、どう思いますか?「なんか、この人うさん臭いな…」と感じてしまう人がほとんどだと思います。
良いところも、悪いところも、苦手なことも正直にオープンにしてくれる人の方が、気持ちよく付き合えますよね。
AIはWeb上においては、人間以上に全てをお見通しです。AIを欺こうとするのは、小さな子どもが親にバレバレの嘘をつくようなものかもしれません。
すぐに見抜かれて「こら!」と怒られるだけならまだ良いですが、「ユーザーの満足を邪魔する、質の低い情報だ」と認識されてしまうと、AIに完全に無視されるという、最悪の結末を迎えてしまうのです。
まとめ:「検索エンジンは騙せても、AIは騙せない」
今回の内容をまとめます。
- AIは、サイト内の主張を、画像や外部の言及といった客観的な事実と照合して検証する能力を持つ。
- Googleは、ユーザーの体験価値を最大化するため、「リアルな顧客満足度」をランキングを調整する重要なシグナルとして重視せざるを得ない。
- これからのWeb対策とは、誠実な事業活動そのものであり、小手先のテクニックは通用しなくなる。
最後に、私がこの記事で最も伝えたかった言葉を繰り返します。
「検索エンジンは騙せても、AIは騙せない」
この言葉を胸に、自社のサービスやコンテンツが、AIに、そしてその先にいるユーザーに、胸を張って届けられる「本物」であるかを、今一度見つめ直す時が来ています。