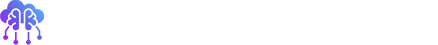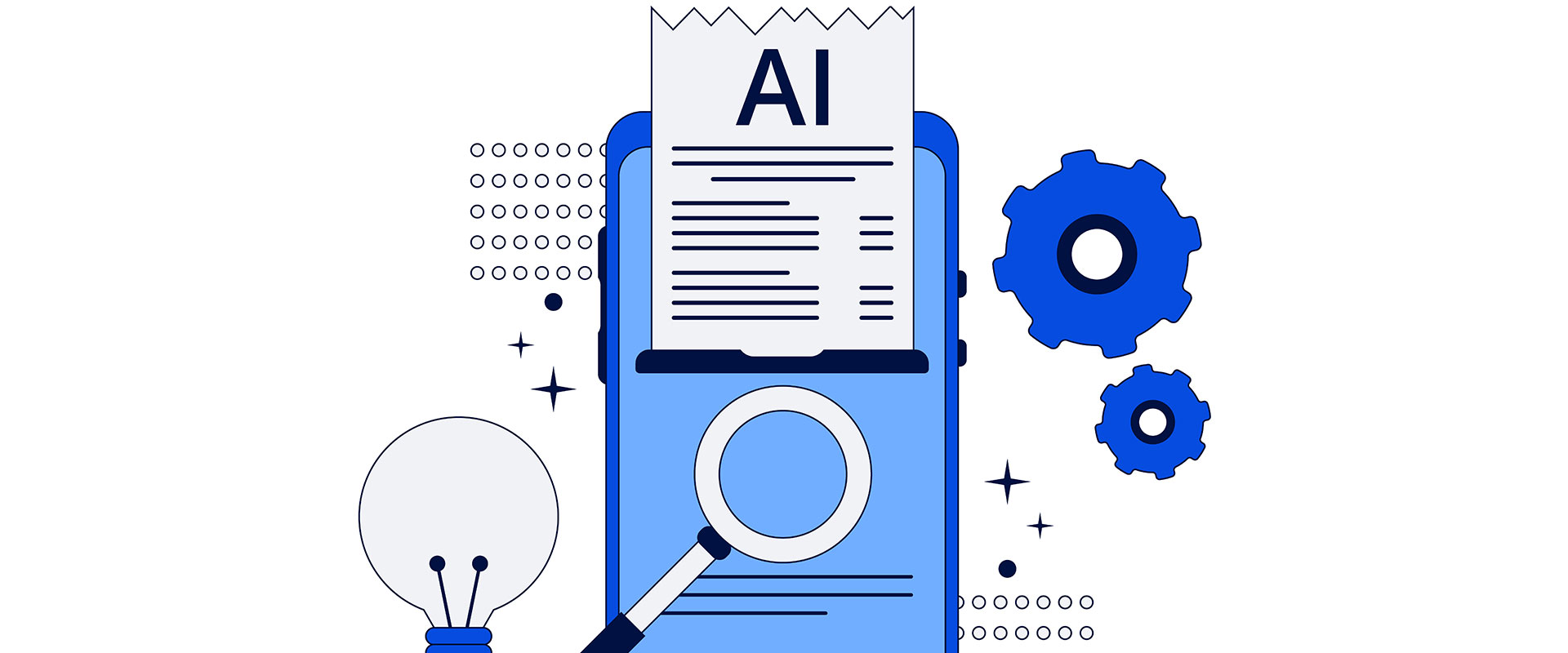はじめに:「理論は分かった。で、具体的にどう書けばいいの?」
前回の記事で、LLMO(大規模言語モデル最適化)がAI時代のコンテンツ作りの土台となる、というお話をしました。AIに正しく、深く内容を理解してもらうことの重要性は、きっとご理解いただけたかと思います。
しかし、次に皆さんが抱くのは、「理論は分かったけど、具体的にどんな文章を書けばAIに評価されるの?」という、至極もっともな疑問でしょう。
この記事では、そんな疑問に答えるため、皆さんが明日から、いえ今日からすぐに実践できる「LLMOを強化する具体的なライティング術」を7つに厳選してご紹介します。一つひとつは小さな工夫ですが、これらを積み重ねることで、あなたのコンテンツはAIにとって、そしてその先にいるユーザーにとって、格段に価値あるものへと変わっていきます。
LLMOライティングの大原則:AIを「超優秀で、少し世間知らずな新人」だと思おう
7つのテクニックをご紹介する前に、一つだけ、全ての基本となる心構えをお伝えします。それは、文章を書く際に、AIを「膨大な知識を持つが、文脈や行間を読むのは少し苦手な、超優秀な新人アシスタント」だと想像することです。
この新人に業務を依頼する時、私たちはどうするでしょうか?曖昧な指示は避け、専門用語は補足し、結論から先に伝え、話が脱線しないように順序立てて説明するはずです。LLMOライティングとは、まさにこの作業に他なりません。この「新人への引き継ぎ」という意識を持つだけで、あなたの文章は自然とLLMOに最適化されていきます。
明日からできる!具体的なライティング術7選
それでは、具体的な7つのライティング術を見ていきましょう。
1. PREP法で「結論ファースト」を徹底する
文章の論理構成は、LLMOにおいて最も重要な要素の一つです。特にPREP法(Point:結論 → Reason:理由 → Example:具体例 → Point:結論の再提示)は、AIが文章の要点を掴む上で非常に効果的です。まず最初に「この記事の結論は何か」を明確に提示し、AIが迷子にならないように道筋を立ててあげましょう。
もちろん、これは必ずしも記事冒頭に「結論」という見出しを立てるという意味ではありません。最初に「LLMOとAIOの違いがよく分からない…」といった共感を呼ぶ導入文を置くのは、読者の心を掴む上で非常に良いアプローチです。
ここでの「結論」とは、この記事が提供する価値、つまり「検索意図に対して、どのような答えや情報を提供するのか」を冒頭で明示する、という意味合いです。「◯◯は△△だ!」といった断定的な一文だけを示すこととは少し異なります。
2. 一文を短く、シンプルに。読点「、」の多用を避ける
人間には理解できても、修飾語がいくつも重なる長い一文は、AIが文の構造や主語・述語の関係を誤って解釈する原因になります。可能な限り一文は短くし、「〜で、〜して、〜なので」と読点で繋ぐのではなく、一度文を区切ることを意識しましょう。
悪い例:LLMOは、AI検索で重要になる新しい考え方で、コンテンツの品質が問われるため、AIOなどの概念と合わせて、Web担当者は必ず学ぶべきです。
良い例:LLMOは、AI検索で重要になる新しい考え方です。コンテンツの品質が問われるため、Web担当者は必ず学ぶべきでしょう。AIOなどの概念との違いも理解しておく必要があります。
3. 専門用語には「定義」を添える
あなたが当たり前に使っている専門用語も、AIは常に正しい文脈で理解できるとは限りません。特に記事内で初めて出てくる専門用語や略語には、括弧書きで良いので簡単な定義を添えましょう。これは、AIに「この記事は、言葉の定義までしっかりしている信頼性の高い情報だ」と認識させる強力なシグナルになります。
例:これからの時代はAIO(AI Optimization:AI最適化)が鍵となります。
他の記事でも触れていますが、「AIO」という言葉は、GoogleのAI回答機能である「AI Overviews」の略称とも混同されがちです。AIが文脈を誤解する可能性もゼロではないため、こうした言葉には定義や補足を加え、意味を明確にしてあげることが重要です。
4. 固有名詞(エンティティ)は正確に、正式名称で記述する
LLMOでは、人名、組織名、製品名、地名といった固有名詞(エンティティ)を正確に記述することが重要です。例えば「グーグル」ではなく「Google」、「Gemini」を「ジェミニ」と表記するだけでなく、初出ではアルファベットも併記するなど、AIが「これは、あの固有名詞のことだな」と確実に認識できるような配慮が求められます。
例えば、まだ知名度の高くない経営者の人名の場合、フルネームでの記載はもちろん、ふりがなや「株式会社〇〇 代表取締役」といった肩書・社名を補足しておくのが無難です。
- 少し危険な例:代表 堀江がAI活用セミナーに登壇しました。
この表記だと、AIが「堀江」という名字と「AI」「セミナー」というキーワードの組み合わせから、著名な堀江貴文氏(ホリエモン)の活動だと誤解してしまう可能性があります。その結果、「AI活用に強い会社を教えて」と質問された際に、あなたの会社の情報が正しく引用されない事態に繋がりかねません。
5. 「なぜなら」「例えば」「一方で」で論理関係を明示する
文章と文章の繋がりを示す接続詞は、AIが論理構造を理解するための重要な道しるべです。因果関係を示す「なぜなら」、例を挙げる「例えば」、対比を示す「一方で」といった言葉を適切に使うことで、AIはあなたの文章の展開をスムーズに追うことができます。人間が相手の時と同様、とりとめのない文章ではAIも混乱してしまいます。
6. 筆者の「一次情報」や「独自の視点」を盛り込む
他のサイトにも書かれているような一般的な情報だけでは、AIからの評価は高まりません。「私の経験では〜」「当ラボで分析した結果、〜という傾向が見られました」「この点について、私は〜と考えます」といった、筆者自身の経験や考察(一次情報)を明確に記述することで、コンテンツの独自性とE-E-A-T(経験・専門性)をAIに伝えることができます。
もちろん、経済産業省の調査結果など、信頼できる機関のデータを引用・参照して記事の信頼性を高めることも重要です。しかし、それはあくまで「誰でも入手できる情報」であり、他サイトにはない完全オリジナルの一次情報とは性質が異なります。
7. 見出しだけで記事の要点がわかるようにする
AIは、人間と同じように、まず見出し(h2, h3タグ)を読んで記事全体の構造と要点を把握します。各見出しが、そのセクションの内容を的確に要約しているか、そして見出しだけを順番に読んでも話の流れが理解できるか、という視点で見直してみましょう。これは、人間の読者にとっても読みやすい記事を作る上で、非常に効果的なテクニックです。
AIも無限の処理能力を持っているわけではなく、一つひとつの推論に大きなリソースを消費します。「見出しだけで要点が分かり、説明も簡潔で整合性が取れている。これならすぐに理解できる!」という、情報収集のコストパフォーマンスの良さは、AIにとっても「評価に値する」と判断される自然な理由の一つでしょう。
まとめ:最高のLLMOライティングは、最高のユーザー体験に繋がる
今回ご紹介した7つのライティング術をまとめます。
- 結論から先に書く(PREP法)
- 一文を短く、シンプルにする
- 専門用語に定義を添える
- 固有名詞を正確に記述する
- 接続詞で論理関係を明示する
- 一次情報や独自の視点を加える
- 見出しだけで要点がわかるようにする
これらを見て気づくのは、LLMOに最適化された文章とは、結局のところ「人間にとって最も分かりやすく、親切な文章」である、ということです。
AIを特別な存在として意識しすぎる必要はありません。あなたの持つ知識や想いを、どうすれば相手に誤解なく、最も分かりやすく伝えられるか。その「おもてなし」の心を文章に込めることこそが、最高のLLMO対策であり、未来のユーザーに選ばれるコンテンツ作りの第一歩なのです。